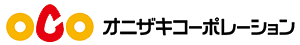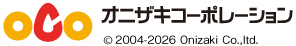ごま屋のはじまり

現在では、「ゴマ」は小袋入り。そのまま使える状態で売られています。
しかし、これは、数千年にも及ぶゴマ利用の長い歴史で考えると、ごく最近のことです。
この物語は、今から50年ほど前、昭和30年代から始まります。この時代、店で売られているのは、産地から入荷したままのゴマ。
さまざまなゴミや砂粒などが混じっています。食べるためには、それぞれの家庭で、ゴミを取り除き、煎って・・と手間をかける必要があります。
オニザキの原点は、こんな時代のゴマの卸売り業者です。
佐賀市のとある雑穀問屋で働いていたお父さんは、ゴマの卸しの仕事をしていましたが、もともとあまり体が丈夫でなかったお父さんは、
ある日、病気になってしまいました。
一家の大黒柱が寝込んでしまい、途方にくれたのはお母さんです。三人の子供をかかえ、 これから生活していかなければならなかったのです。
そこでお母さんは、このゴマを手で洗い、小さなごみを一つ一つ丁寧に手で取り除いて
小売店へ卸す仕事を始めました。自宅で出来ることはそれしか思いつかなかったのです。洗ったゴマは日光にあてて充分に乾かします。
天気の日には庭いっぱいに広げた ござの上でごみを取り除くお母さんの姿が見えました。 袋に詰めたゴマを自転車で配達し、帰ってくるとゴマを洗う。そんな毎日でした。
ごみの混ざっていないゴマは大変好評で、少しずつ注文が増えました。
そのうち小売店から「いりごま」や「すりごま」の注文が入るようになり、
お母さんの仕事は忙しくなっていきました。大きな中華鍋でゴマを煎ったり、すりばちでゴマをすったり、
それまで家庭で行われていたことが、商品に求められはじめたのです。日本が豊かになろうとした時代です。